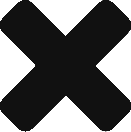ぼーっと見て良かった。結果的にワールドカップを楽しめたのだからこの見方は正解だった。どんなに素晴らしい能力を有したプレイヤーであっても、1ヶ月かそこらで作られた即席チーム同士の試合では本来の実力は発揮されない。サッカーはチームスポーツであり、チームとして機能して初めて、個の能力が発揮される余地が生まれる。数々のスタープレイヤーが窮して単騎で突撃して散る様を何度見たか。数年かけて熟成された100点満点近いチームにおいて、メッシやロナウドのような100点前後のプレイヤーは機能する。80点の代表チームでは、チームそのものがボトルネックとなってしまう。
だがそれこそがワールドカップ・代表チームの見方だと、今回のぼーっと見たワールドカップを通して感じるようになっていった。100点満点同士のタイトさとはまた違った、80点同士のブレや遊び幅が、サッカー的な番狂わせを生み出す。もちろんそこに魅力が生じるようになったら元も子もなく、あまり望ましくない状況だが、短期集中トーナメントではまた一つの魅力のように感じられたのが正直なところだ。
そんな中でチームとして機能し、その上で個の能力が発揮されたスペイン・ドイツ・ウルグアイあたりが最後まで残ったのは順当な結果だと言える。スペインはアラゴネスがEUROで作り上げたチームをデルボスケが引き継ぎ、またカプデビラ・トーレスを除く先発固定メンバーがバルサとレアル。ドイツは前回のクリンスマンのチームの実質的コーチであったヨアヒム・ルーフがそのまま4年かけてチームを熟成させていた。ウルグアイは南米という事情柄、元々守備(=組織力)の実力は高く、今回たまたまそれにフォルラン・スアレス・カバーニのような優れたフォワードがいただけだ。
逆にフランスは個が大勢いてもチームとして機能できなかったし、イタリアには個がいなかった。アフリカは、地元の利を自らブブゼラの騒音でフラットにした。あの楽器はまさしく騒音で、果たして応援したいのかブーイングなのかわかりずらい。まあJリーグ初期に「オーレーオレオレオレー」つってラッパ吹いてた日本人に言われたくないだろうが。
また希有な個はいないが、チームとして機能したスロバキア・日本・韓国・アメリカ・チリ・パラグアイが大会の帰趨を大きく左右した。グループリーグ、スロバキア・アメリカは劇的な方法によって、また日本・韓国・チリ・パラグアイはチーム力の結実としてそれぞれRound16に進出した。中でもスロバキア – イタリアは、イタリアの凋落ぶりを見事に示した、しょっぱい試合だらけのグループリーグの中でもワールドカップらしいブレ幅の大きい白熱した試合だった。

しょっぱい原因は何か。ジャブラニ。確かに本田やフォルランが蹴った、野球のナックルボールのようなフリーキックを生み出し、流れの中のシュートでもキーパーの逆を付いたりして(日本的にはオランダ戦の決勝点)、そういう意味では当初の狙いも一部達成されている。だがほとんどのシーンではボールの扱いづらさに多くのプレイヤーが難儀し、見る側にとっても可能性ゼロのシュート・クロス・フリーキックが目立って興が削がれ、結果的にはボールの”改良”が裏目に出てしまった。
急造スタジアム。今大会がおそらく全試合HD画質で放送された初の大会だと思うが、SDと大きく違うのは選手の顔がよく見えるではなく、芝目が結構よく見えることだ。会場名を把握して試合を見なかったのでどこがどれほどとは言えないが、とにかくグラウンドは全体的にボコボコ、試合後は穴ぼこだらけというのが印象に残った。
負けない意識。優勝候補チームのプレイヤーが、リーグ戦の疲労を残したままワールドカップに突入したため、「グループリーグを利用しながら調子を上げていく」というイタリア伝統みたいな方法を採らざるをえず、それでも勝ち点は積み上げねばならないので「先制点を奪われないこと」を最優先していた。それが結果的に調子の上がらなかったチーム、そもそも実力がなかったチームを生み出し、各試合かなりばらつきが生じた。優勝したスペインも初戦スイスに負けている。それも攻めて攻めて点が取れず、スイスの一つのカウンターで敗れるという典型的な方法で。地上波では放送されなかったようだが、全64試合の中でも、負けない意識の薄い三決・ドイツ – ウルグアイが試合としては一番面白かったという皮肉。勝つ意識を持てれば攻撃的な試合をできるチームなのに、負けない意識が作用してしょっぱくなってしまった。
決勝トーナメントに入ってからは、調子も上がり面白い試合が多かった。全て好ゲーム。それぞれに、サッカーがもつ様々な魅力を感じられた。中でもオランダ – ブラジルは、リスク管理や試合マネジメントという側面において、何度見ても面白いと思う。最高の出来だった前半のブラジルが、ハーフタイムでオランダをなめて、対するオランダは決死の覚悟をもって後半突入、アクシデンタルな失点~うやむやの決勝点~メロの退場、つまらないブラジルを選んだドゥンガの哲学が崩壊する瞬間。その顔。ダサいファッション。よく言う「流れ」の重要性や、結局サッカーはメンタルスポーツであることが、実証された試合だった。
そうしてサッカー的な勝利で決勝まで進んだオランダと、優勝候補が順当に調子を上げて、今大会ベストチームのドイツすらも退けて進んだスペインのファイナルでは、パススピードとトラップの正確さで両チームのレベルの高さはよくわかった。結果スペインが優勝したが、この試合もオランダのゲームマネジメントが展開を左右した。
個々のタレントを見ると、攻撃側ではオランダもスペインも、方法は違うが遜色ない。対して守備(組織)側では明らかにスペインに分がある。バルサの2センターと世界最高のGKカシージャス。中盤はバルサのトリデンテにXアロンソの展開力。対してオランダはどっかの馬の骨的センターとGK、中盤は世界最高のスナイデルに壊し屋二人。五分の勝負をしては勝ち目がないと判断したオランダが、ラフプレイを連発して試合を壊した。いつものパス回しが悪質なファウルで潰されリズムが生まれないスペインに対し、オランダの速攻は効果的だった。
だが結果的には、この作戦がオランダに不利に作用したかもしれない。それも含めての賭けだったかもしれないが。イエローカードの判定はほぼ順当に感じた。オランダは主審とも駆け引きをしていた。中には一発レッドでおかしくないファウルが、ワールドカップファイナルという性質上、イエローに止まったものもある。90分終了時のカード数はオランダ6・スペイン3。延長では合計5枚出た。その中で延長後半にハイティンガが累積退場。ファイナルの主審を務めたのはハワード・ウェブのイングランドセット。4thに日本の西村さん。プレミアリーグを見る人はよく知っているが、ハワード・ウェブははっきり言ってザルだ。終了間際の重要な場面で、ザルっぷりを存分に発揮した。だが大会を通じてよくわかるように、それもサッカーである。


審判の誤審問題も色々出たなあそういえば。ランパードのシュートやテベスのオフサイドで大騒ぎしたのもなんか懐かしい。いやそういう問題じゃない。ランパードの幻のゴールについては後日談というか、過去の因縁話があったりして、本当に面白い。1966イングランド大会ファイナルでの疑惑のゴールが、44年後に解消されるとは、なんてドラマチックなんだ。そういう文脈で理解もできるが、これまたそういう問題じゃない。
判定に機械を導入するかの是非は昔からあって、FIFAもアンダーの大会でボールにチップを埋めたりゴールラインに専用の審判を配置したりして実験した結果、「現時点では必要なし」と判断している。詳しい経緯は知らないが、個人的にはサッカーのオリジナルから考えて、必要であれば機械の導入も審判増加も積極的に行うべきだと思う。つまり本来サッカーに審判はいなかった。オフサイドもなかった。選手交代も出来ず、骨折したままプレイした人もいたらしい。またむしろ審判がいない方が、互いに気をつけていたのでファウルも少なかったという話もある。
ルールの整備を行ううちに、これら追加ルールが設けられたわけで、であれば金科玉条ではなく不都合であれば柔軟に変更するべきだ。前述した二例の場合、ランパードのゴール見逃しについては、ゴールラインという定点観測なので、むしろ機械で厳密にやった方が絶対に良い。具体的にはゴールラインを完全に割った時点で主審に信号が届くとか。なんならGPSでミクロ単位でゴールラインを捕捉してもいいだろう。ただテベスのオフサイドは現状機械では難しい気がする。今のルールでは「ボールに積極的に関与したかどうか」がオフサイドの判定基準なので、その曖昧さを機械で判断するのは困難だし、ゴールラインとは違ってオフサイドラインは絶えず上下動するため捕捉が難しい。
まあー、、、ざっとこんな感じかな。最初に書いたが全然期待してなかったのもあってか、終わってみればかなり面白い大会だった。この感じは試合のクオリティだけでなく、その周辺も併せてのものだと思う。以下気になった点を挙げてみよう。
・今大会のスカパー

スカパーで見るのは2002年から3回目だが、それぞれに(地上波と比べると金銭的しょぼさは感じられるが)周辺の内容が充実していた。2002年のジャーナル、2006年のデータスタジオ、そして2010年のジャンルカなうと、誰もが楽しめるサッカー番組を提供してくれた。
長くなりそうなので以下列挙 赤=特にインプレッシブ
・マラドーナ

-ゲイではありませんよ。ベロニカです。金髪です。
-マンクーソ・エンリケとのトリオ
-十字7回
-サムエルにウザがられる
-どう見ても酔っぱらい
・オシムじいちゃん

-・・・Fu
-エゴイストがいる
-私も戦っていましたよ。世界が終わったわけではありません。
-バルカンシンドローム
-オシムTwitter
–ハニュウか?
-オスシ
-野々村の切り込み
・Ke-Nako-
・ブブゼラうるさい
・ジャブラニクソすぎ
・ワールドカップ史上最悪の誤審 → 1966年ハーストの因縁
・パッカくん
・桃色ハピニャス
・素人目線っちゃあ素人目線
・amie VS ミック・ジャガー
・タコのパウルくん
・子供店長とかいう糞餓鬼
・エグザイルの歌覚えたくない
・アンビシャス覚えたくない
・見せてくれ内田 ←見れない
・アクエリアスの一人勝ち
・HDのダンディ
・サムエルのブロック
・チョンテセ号泣
・本田ドヤ顔
・ドメネク死亡
・イタリア死亡
・バティ盗難
・オリベイラのガン見
・青いセーター
・娘のコーディネイト
・ドイツの変化
・ハムシクだけパンク
・ドノヴァンかっこよすぎ

・邪悪なお兄さんフォルラン
・フォルランの漢気
・大会前に注目していた平畠はさすが。乗っかり芸能人とは違う。
・スアレスのレシーブ
・ギャンのPK
・ギャンとザクミ
・ごっつぁんパレルモ
・テリー鮪
・ロッベンがさらにじいちゃんになっている
・アメリカ国歌斉唱の肩組み
・グリーンやっちゃった
・松井もっと良いチームに移籍して欲しい
・日本についてはきちんとトレースしていた連中が分析・評価するだろう
・マイコンみたいなサイドバックがいると超楽
・メッシ/ルーニー/トーレス がノーゴール
最後に俺的大会ベストメンバー
フォーメーション:4-3-3
FWフォルラン
(ギャン・アルティドール)
FWビジャ FWロッベン(ミュラー・イニエスタ)
MFエジル(ドノヴァン) MFスナイデル(チャビ)
MFシュバインシュタイガー((Xアロンソ)
DFフシレ(ラーム) DFマイコン(ラーム)
DFプジョル DFルシオ
←←←テリー
GKカシージャス(ノイアー)
スアレス
監督:マラドーナ |
フォーメーションは今大会を象徴する4-3-3。このシステムは近年バルセロナやインテルで採用されたトレンドが、代表にも反映されている。伝統的なオランダ型4-3-3との一番の違いは両ワイド。典型的ウインガーではなく、中に切り込んでシュートを撃つフォワードやセカンドトップが配置される。
中盤の3人は流動的で、高い運動量と確かな技術を求められる、このフォーメーションでは一番難しいポジションだ。3人とも10番と5番の役割を兼務し、前の3人とも連動して攻撃する。最近では試合後にどれくらいの距離を走ったかのデータが出るが、大抵この3人が12km前後走っている。
守備の4人は役割としては4-4-2と同じだが、ここも中盤と連動するのでラインは高くなりがちだ。よってセンターの2人は足が速い。
ゴールキーパーも守備ラインと連動するので、捕球だけでなく足元が上手くないと使えない。ボールが軽量化したおかげで、キーパーからのロングキックやロングスローが重要な攻撃の起点となっている。
各プレイヤーそれぞれについても触れたいが長くなるのでこれで終わり。
現時点での結論:
ワールドカップは始まってから急に見るととても面白い